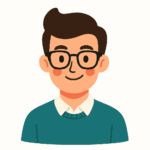
こんにちは。よしです。
指標(ファンダメンタルズ)の大切さ
株はよく人気投票といわれ、時流に乗った銘柄やテーマ株が高値をつけます。しかしながら、そういった株の株価を裏付けるものは話題性や将来性以外には乏しく、時には補助金ありきで事業が成り立っていて本業で稼ぐ力がまだない企業だったりしていることもあります。そのような企業が上場していてよいのかという話はともかくとして、数値や事実に基づいた情報を根拠にできればよいのですが、なぜ人気投票になるかといえば人はバイアスに振り回されるものだからです。バイアスに振り回されないために、数値という確固たるものを指標にしましょう。
ここでは、私が参照している指標とその見方・考え方に関して紹介します。市場は理想的には全員が合理的に動き、全企業が適切な価格付けとなっているものですが、実際はそんなことはなく、成長が見込めるのみ割安な銘柄が存在します。
そのような銘柄を見つける方法の一つとして、指標を確認することをおすすめします。指標によって現在の企業の状態を確認し、自分が描く将来ストーリーに沿って利益を生み出しそうかどうかを判断します。検討の結果投資に至った場合、このとき描いたストーリーは売却タイミングを計る指標にもなります。描いたストーリーから下振れた際や成長の方向性が異なる際がそのタイミングとなります。
各種指標は企業の現在の姿を詳しく表す
さて、私が良く確認する各種指標を紹介します。これら指標は、企業の現在の状態を表す通信簿です。少し堅く、である調にしています。
PER (Price Earning Ratio):当期純利益と時価総額の比。低いほど割安とみなされる。
より詳しく知りたい方向け
業種によって平均PERが異なる。これは、将来成長する市場であるという期待値が業種によって異なるからである。PERが低いことは今現在の利益に関しては相対的に割安であることに変わりはないが、将来CF(キャッシュフロー)を考慮した際にNPV(現在価値)が割安となるとは限らない。また、一過性の利益(特別利益)に左右される点は要注意。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
業界ごとの平均値や市場の平均値は投資家心理やマクロ環境によって変動するため、細かく計算するときりがない。個別銘柄の過去5年程度のPERの変動をみてその銘柄として割安圏(売却時は割高圏)かどうか判断。極端に下がっている場合は特別な理由がないかをIR(Investor Relations)を中心に確認する必要がある。過去日経平均PERは10-15倍程度を推移(バブル時は約60倍)しており、10倍以下は割安と簡易的に判断している。
PBR (Price Book Ratio):資産と時価総額の比。低いほど株価が過小評価されていることになる。
より詳しく知りたい方向け
PBR1倍以下の企業は時価総額が解散価値(企業が保有する資産を売却して生み出される価値)を下回ることになり、理論的には事業活動をすることで社会に貢献していないことになるため事業を続けず、解散したほうが価値が高く社会のためになる企業であるということになる。とはいえ、市場に流入する資金の総額は青天井ではないため不人気企業であればPBR1倍以下の企業は発生し得る。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
のれんをはじめとする無形固定資産を除き、資産の価値は、その資産を有効活用することによって生み出されるキャッシュを基に求められる。よってPBRが低い企業は理論的に稼ぐ力に対して株価が低い(割安)ということになる。実際にPBR = PER × ROEという計算式が成り立つ。一般的に有形固定資産が多めの企業(メーカー等)は低め、無形固定資産が多めの企業(IT等)は高めになりうる(そして、無形固定資産の方が減損しやすい傾向がある)。過去日経平均PBRは1-1.5倍程度を推移(バブル時は約5.5倍)しており、1倍以下は割安と簡易的に判断。東京証券取引所はPBR1倍割れ(と1倍台銘柄が多いこと)を問題視しており、企業へ改善を求めており、株価の上昇がPBRの向上につながるためROEの向上による投資価値の向上や自社株買いによるPER改善による株価上昇を各社提案している。PBR1倍割れに関して何もコメントしていない企業より、対応策を明示している企業の方が投資対象としては相応しいと考えている。
PER×PBR:PERとPBRの積。低いほど割安判断ができる。
より詳しく知りたい方向け
低ければ低いほど割安。バフェット氏の師匠のグレアム氏は購入する銘柄として経験則から「PBR×PER< 22.5」を推奨しています。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
両者の積を見ることで、より客観的な判断が可能となる。PER×PBRをした際に、一定以上の数値となるのは①PERが低くてPBRが高い、②PERが高くてPBRが低い、③PERもPBRも高いの3パターンとなる。①は資産効率が良いパターンだが、積が大きい場合は資産が将来にわたり稼ぐ力を過大評価している可能性がある。②は将来生み出すキャッシュを市場が過少評価しているパターンで、現在稼げていない状態において将来稼げるかに疑問が残る。③は①と②のリスクを内包しておりリスクが増える。私は簡易的には10倍を基準にしている。10倍以上は投資対象なり得ないという意味ではないく、10倍以下をかなり割安と判断するという意味である。
EV/EBITDA:時価総額とキャッシュ
より詳しく知りたい方向け
EBITDAは利払いや法人税や償却前のキャッシュを見ることができ、国や事業環境によって異なるこれらの要素を取り除いて稼ぐ力をみることが可能。EBITDAだけでは事業規模の影響が出るが、時価総額との比とすることで割安・割高の指標とすることが可能。設備投資の多い新設企業や成長企業の稼ぐ力を評価しやすい。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
EBITDAは企業が生み出すキャッシュを表しており、M&AではしばしEBITDA倍率を用いて企業価値が算出される。将来の成長を見越していれば倍率は高く、成熟企業では低くなる。企業や事業のステージによってEV/EBITDAの数値は変わりうるが私は10倍を基準としている。
ROIC (Return On Invested Capital):投下した資金ででどれだけ利益を上げているかを表す。高いほど少ない資金で利益を上げていることになる。
より詳しく知りたい方向け
NOPAT(税後営業利益)と「株主資本と有利子負債」の比で稼ぐ力を表している。資本コストを考慮せず投下資本に対する収益性を見ている点が特徴。ROICが高い方が収益性は高いことは間違いないが、投下資本を増やせば収益性が上がるというわけでもない点は注意が必要。企業は最適な数値を模索することになる。ROAは掛金の影響が数値に入り、ROEはレバレッジが数値に影響するがROICはその影響は取り除くことができる。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
営業利益率は収入を分母とするため、真の稼ぐ力が見えにくいことがある。ROICを指標とすることで投下資本に対する利益を見ることができる点は面白い。一方で有利子負債とエクイティ(株主資本)の比率はROICだけでは見えず、自己資本比率やWACCとの相互評価が必要となる。私は簡易的に10%を基準としている。
ROE (Return On Equity):当期純利益と自己資本の比。高いほど自己資本に対する利益が多いことになる。
より詳しく知りたい方向け
レバレッジ(負債割合)が高ければ高いほど自己資本が少なくなり、ROEは向上する。事業の安定性とのトレードオフという指標でもある。また、PBR=PER×ROEという式が成り立ち、PERが低くROEが高い場合高収益で割安な企業といえるというわかりやすい指標あり。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
自己資本比率との兼ね合いとなるが、高いに越したことはない。私は10%を基準としている。その際の自己資本比率は50%以上であることが望ましい。
自己資本比率:総資産に対して自己資本が占める割合。自己資本以外は他人資本(負債)となり返済義務があるため、比率が高いほど財務健全性が高いということになる。
より詳しく知りたい方向け
業種によって偏りがある。一般的には事業が安定している企業ほど安定して利払いを行えるため(≒信用力があるため)自己資本比率は低くなる。また、銀行借入に代表される負債の方が期待リターンが低いため(倒産時等の弁済順位が株式より高く、回収不能リスクが低いため)、自己資本比率が低いほど稼げる企業になりうる。一方で、分配が柔軟な株式への配当とは異なり利払いは期限の定めがあるものが多いため、適切な自己資本比率を保つことが財務健全性のために重要となる。また、銀行は負債となる預金の関係で自己資本比率は低くなる。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
銀行等一部除き、高いに越したことはないと考える。ROEとの兼ね合いで判断するが、私は50%以上を基準としている。数値より、過去比自己資本比率が悪化していないかは重要視している。
営業利益率:売上と営業利益の比、本業で稼ぐ力を表す。
より詳しく知りたい方向け
業種によって営業利益に組み込めるものと組み込めないもの(経常利益に組み込む)に差異がある。金利による収支や投資による収益は一般的に営業外費用に計上され、自己資本比率が低い金融業などは営業利益を見るより経常利益を見る方が指標として適切な場合もある。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
営業利益率が高いということは、それだけ本業で稼ぐ力があるということになる。仮に、従業員の給与が増えたり急な支出が発生しても吸収できる利益を生み出す体質ができている。本業が過渡期になり研究開発費が増大しても利益を出せることになり、環境の変化に対応できることで競争に勝ちやすい企業でもある。参入障壁が低い産業や競合が多い企業は価格競争となることで営業利益率が下がる傾向があり、反対に営業利益率が高いということは結果競争力があり、独占または寡占な環境で有望な事業をしていることを表しているとも考えられる。私は10%を簡易的な基準としている。
配当性向:利益に占める配当分配率。低いほど財務健全性が高く減配率が低い。
より詳しく知りたい方向け
成長企業では、利益を全て成長に費やす方が株主価値を高めることにつながるという思想の元、無配としている企業も多い。一方で逆の考えから成熟企業は配当を分配する。設備の修繕費が適切に積まれ、今後の配当に影響がないかを確認することが重要。配当性向を見ることでバッファーがあるか確認可能。配当性向のほかに、自社株買いも含めた総還元性向を指標とすることも多い。ただし、総還元性向は期によってばらつきがあることが多いため、配当性向を指標としている場面の方が多い。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
業種や企業の成長ステージによって変動するが私は50%を基準としている。配当が出始めもしくは増配が始まり配当性向が20-30%のタイミングで投資し、将来的には配当性向の引き上げによって40%程度になる、もしくは積極的な自社株買いが行われるのが理想である。
配当利回り:株価と配当金額の比。高いほど配当で回収できるリターン(インカムゲイン)が多い。
より詳しく知りたい方向け
一般的には2%が平均的な利回りとなる。3%を超えると高配当といえるだろう。配当利回りはわかりやすい指標のため、利回りが5%を超える水準で放置されている銘柄は、期限付きの分配か事業環境にリスクを抱えていると考えるのが妥当。過度な分配でないか配当性向も確認することも重要となる。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
モチベーションの確保と利益確定の観点から、配当がある銘柄に投資した方が良いと考えている。最低でも1%あるのが望ましく、私は2.5%以上を基準としている。配当利回りが適切かの判断が難しいが、配当利回りが高いという事実は割安の一つの基準となるほか、株価下支えにつながる。
フリーキャッシュフロー:余裕資金がどの程度あるかの指標。プラスが多ければ、借入金の返済や株主への配当、投資等に活用でき、財務健全性が高い。
より詳しく知りたい方向け
営業キャッシュフローから投資キャッシュフローを引くことで算出できる。企業が自由に使えるお金であり、フリーキャッシュフローを用いて企業価値を算出することもある。キャッシュフロー経営をすることで財務安定につながる。キャッシュフロー経営をしている代表的な企業の一つに米アマゾンがある。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
フリーキャッシュフローがプラスであることは、それだけ事業が安定していること、キャッシュフローを考慮した経営をしているということになる。私はできるだけフリーキャッシュフローがプラスの期間が長い(もしくは多い)かを気にしている。
WACC(Weighted Average Cost of Capital):借入にかかるコストと株式の調達にかかるコストを加重平均したもので事業活動の期待リターンの目安となる。ROICを上回れば期待値以上のリターンをあげていることになる。
より詳しく知りたい方向け
定性的なものではなく、業界や、株主の期待リターンによって変わりうる。負債と株主資本の割合、その時々の実効税率、金利状況や株主が求めるリターンが変数となる。金利の上昇や株主が求めるリターンが高いほどWACCも高くなる。
管理人よしの考え方を知りたい方向け
WACCを算出し、ROICと比較すること自体は悪くない。一方で、WACCの算出自体曖昧で仮定が入るものであるという事実がある。単純にROICと比較するのではなく、各企業のWACCがどのような考え方で算出されているかを理解できていなければ参考にしてはいけない情報だと考える。負債比率が上がれば、WACCは下がる一方でROICは影響を受けない。事業によって適切とされる負債比率が異なり、業界によってWACCとROICの関係も変わるということは理解しておく必要がある。
etc. 適宜追加します。
企業の将来性を予測することはできるか?
企業の現在はここまでの定量化された各種指標である程度つかむことができます。一方で、将来性や未来を予測することはできるのでしょうか?もちろん難しいですが、今ある情報から予兆はつかむことはできます。
成長株投資の神様フィッシャー氏は、著書「株式投資で普通でない利益を得る」で企業を調べるべき15のポイントを挙げており、いくつか紹介します。言葉は私の解釈に変えています。
- 市場規模の拡大が期待できる事業か
- 経営陣に気骨があるか
- 研究開発力があるか
- 物流や販売が効率的か
- 利益率は高いか
- 利益率を維持するための施策をしているか
- コスト管理は適切か
- 長期的な視点を持っているか
機関投資家でないと(もしくは機関投資家でもなかなか)手に入れられない情報や客観性に乏しくなるものを外しました。記載したものも、原題の情報社会といえどもなかなか集めることは難しいですし、集めた情報の解釈や真贋をどのように判断するかという問題も常にはらんでいます。挙げている項目はどれも企業の成長と競争力確保に重要なもので、確かにこれらの情報が把握できれば、未来の予兆をつかむことはできそうです。
一方で、定性的に理解することは難しいため、経験則や情報収集スキルを上げるというのが重要で、答え合わせも結果論なのか考察道理なのか判断が難しいため、未来の予測はなかなか難しく、足元の数値を基に判断するのがまず大事というのが私の意見です。
まとめ
今回は各種指標に関して紹介しました。未来が分かれば簡単ですが、やはりなかなか難しいというのが私の意見です。現在明らかになっている指標を基準とし、成長性や利益に比して割安だと思える銘柄を探すのがリスク比のリターン最大化を目指す近道だと考えます。トライアンドエラーあるのみです。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
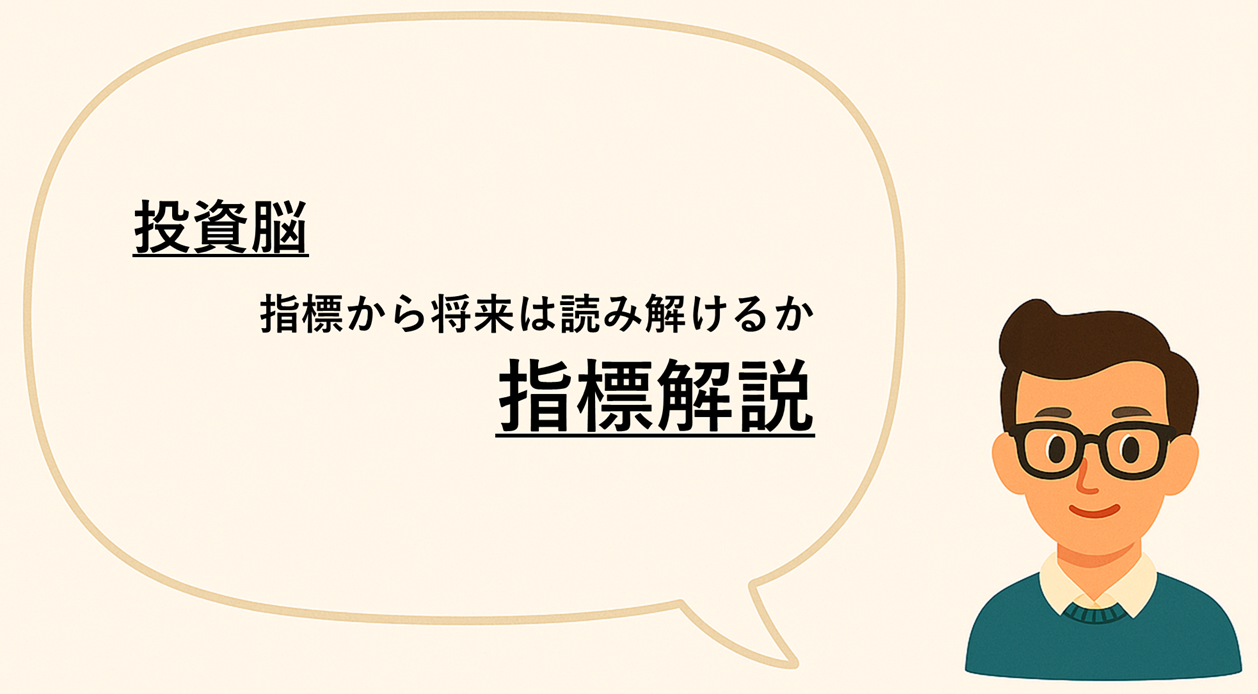
コメント