
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年12月現在1.5億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
私の売買の基準と考え方を共有します。
まず、優先して考えていること。
常に根本にある考え方は、「出来るだけストレスを感じないようにする」です。
株式投資でストレスを感じるときと言えば、大きな含み損がある時ではないでしょうか?
私は20258月時点で約140銘柄を保有していますが、そのうち含み損の銘柄は20銘柄を切っています。
損失額は5%以下の銘柄が大半を占めており、取得したばかりの銘柄、もしくはすでに配当を受領しており実質プラスの銘柄で構成されています。
-10%以上の銘柄はジャパンクラフトホールディングスでして、現状優待で元は取れている状況です。もちろん株単体で利益を出せるに越したことはないのですが。。
| 損益率 | 銘柄数 |
| -20%以上 | 0 |
| -20%~-10% | 1 |
| -10%~0% | 17 |
| 0%~10% | 43 |
| 10%~20% | 27 |
| 20%以上 | 54 |
なぜ大きく含み損を抱える銘柄が少ないのか。
話を「出来るだけストレスを感じないようにする」に戻します。
投資をしながらストレスを出来るだけ感じないようにするにはほったらかしか積み立て投資をするというのが簡単だと思いますが、ここでは優待が欲しくて個別株も見ている人や積立以外もやってみたいから個別株に投資したい人が読んでいるという前提で話をします。
私はポートフォリオの大半がプラスになっており、含み益を抱えている状況から日々の多少の値動きは気になりません。
どうやってその状態を実現しているかといえば理由は大きく3つ、
- 保有期間が長い銘柄が多いから
- できるだけ安いときに買っているから
- 損切をしているから
当たり前で、単純なことかと感じるかもしれません。それぞれ、私の投資手法を交えてご説明します。
保有期間が長ければプラスになりやすい
1つ目「保有期間が長い銘柄が多いから」をすごく簡略化いたしますと。
世界人口増加
↓
ものやサービスの需要増(よほどいらないものでない限り)
↓
物価は緩やかにインフレし高くなる(短期では増減有)
↓
企業の売上増加(同じく短期では増減有)
↓
利益増加(市場環境が変わらず、売上に対しての利益率は一定の前提)
↓
株価上昇(同一PER仮定)
という流れになるため、株価は右肩上がりになります。
株式を介さない資金調達が主流になったりすればこの流れは崩壊するのですが、結局代替となった手段で似たようなことが起きるはずです。
長期では右肩上がりという法則が成り立たなくなるような場合は経済が崩壊し通常の生活が長らく困難になる時だと考えています。
よって保有期間が長ければ長いほど株価は上昇するのが一般的です。
一方で日本株がバブル崩壊から30年以上日経平均最高値を更新しなかったという事実もあり、これは日本が長らくデフレであったことから説明はつくのですが世界的な物価上昇は文字通り世界規模で考えた場合であり、日本という国単位でさえ成り立たない(正確には長期保有が30年以上である)場合があることには注意が必要です。
実際、バークシャーハサウェイによると1965~2023年までのS&P500種株価指数の年平均リターンは10.2%(配当込)だったということで、複利で計算すると投資資産が7年後にほぼ2倍になる計算となります。
当該期間に米国のインフレ率は10%を超えることはあまりなく、多くは1%台~3%台でしたので投資をしていた方は大きく資産額を伸ばしたことでしょう。
できるだけ安いときに買うには
2つめの「できるだけ安いときに買っているから」を説明します。
実際問題、株価が底であるときに買うことはできないと思います。
ただ、比較的安く買うことは出来ます。
例えば、「事故は買い。事件は売り。」という有名な格言が参考にできます。
「なんらかのイベントで株価が下落した際に、短期でしか影響しない事故で再現性があまりないもの(例えば、地震による軽度の機器破損等)は買い。
一方企業体質が基で、長期で影響し再発するような事件(例えば、隠ぺい等)は長期で業績に影響を与えるため売り。」という意味です。
株価は将来の利益を反映したものですので、株価の下落が短気な事象によるものであれば当然買いという判断になります。
ざっくり数値で説明すると、ある事象が将来にわたり”ずっと“年間利益を5%下げるものであれば、現在の株価が5%下がるのは妥当です。一方で”1年のみ“年間利益が5%下がりますというものであれば、株価が5%下がった場合当然買いです。
長期利益を積み上げただ際に今年だけの5%下落は微小だからです。
株価が下がった際は、「今後も下がったらどうしよう。」と不安になることもあるかと思います。
物事を理解すれば不安は減るかなと思いますので、長期でみれば株価は上がるという考えに似ていますが補足します。
必要なものは必ず需要が生まれます。ですので、一時的に株価が下がろうともまた上がります。
俗にディフェンシブ銘柄といわれる電力や交通といった基幹インフラはこのような考え方ができる代表例となります。
そのほかにも、急になくなったら生活できない(=生きていくことが困難、もしくは著しく不便となる)ものはディフェンシブ銘柄と考えることが可能です。
一方で、本当に今後も必要なものなのかという検証の際には判断にバイアスが働いていないか客観的に評価することが重要です。
ここまでは理屈の話で、実際どう対応するかという話ですよね。
私がどうしているかを紹介しておきます。
応援したいとか、最近よく目にするとか理由はなんでもよいので、事前に欲しい銘柄に目星をつけておきます。
そして目星をつけている銘柄が前日比で3%以上下落した際に、理由を確認します。値下がりに理由がつかなかったり下げすぎと考えられる際は”買い”の可能性が高いです。
楽天証券やYahooファイナンスでアラートが設定できるので興味がある方は登録の仕方を調べてみてください。
2025年ですと、
花王の2025年4月11日(前日比-7.6%→翌日+3.1%)
村田製作所の2025年5月1日(前日比-12.8%→翌日+3.1%)
等が私が安く変えた銘柄となります。
損切をするには
最後の「損切をしているから」を説明します。
よく、自分でルールを決めて取得価額から-10%以上下がったら損切とかありますよね。
私は、買った時点でそれなりに安いという前提で買っているので単純な値下がりでは損切しません。それがマイルールです。むしろ買い増します。
損切するときは「想定していた前提条件が崩れたとき」か「ほかに買いたい銘柄があって現金が欲しいとき」のパターンが多いです。後者は利確の際の理由にも使います。
値下がりした株の買い増した分だけで考えて利益が出ていれば、いったん(平均取得金額からすると損でも)現金化することもよくあります。
ほかに買いたい銘柄があるからです。売却後再度下がれば買い増しますし、上がれば含み益を抱えた状態で安心して過ごせます。
株主優待や配当利回りが相対的に高い銘柄を好んで取得しますので、利益がでて株主への分配さえしっかりとされていれば短期の株価は気にせず配当や優待を享受するのみです。
値下がりしても、下落に理由がなければ価格は戻ります。
値下がった理由の本質に気づけず、買い増してしまったこともありますが、本質に気づいた段階で(その金額が下落価格と照らし合わせて妥当か考慮したうえで)売ります。
それができるかという話かもしれませんが、自分の中で買う際に基準を決めておくというのがやはりひとつの指標になるかと思います。
冒頭の例でいえば-10%の価格下落、私は前提条件からの乖離ですね。
私は新規銘柄購入時は複数単元購入して、価格上昇時は優待基準等を考慮しつつ一部売却して利益を確定。残りを中長期保有分として残します。
中長期では株価は上がりますので、含み益を抱えた銘柄が増えていき、短期で値下がり割安となった銘柄の取得で資産を増やしていく。
こうしてストレスを出来るだけ減らして投資をしています。
まとめ
ここまでの話で気づいた方はいるかもしれません。
積み立て投資の案内でよく取り上げられるドルコスト平均法を定期積立ではなく、自分でやっているだけです。
①安いと判断して購入したい銘柄を、②昨日より安くなった際に、③安くなった理由を考えたうえで購入する。以上です。
理由がない下げであればランダムウォークによるものと判断して買い。理由があったとしても必要以上の下げなら買いという具合ですね。
ドルコスト平均法は積立時が短期で見て割安かは考えず、長期で株価が上がるという前提での投資手法です。
私の手法では、ドルコスト平均法に比して短期でも相対的に割安のタイミングで購入できる可能性が高くなります。
まとめると、私のマイルールは以下となります。
- 購入候補を事前にまとめておく
- 前日比3%以上下がっている場合理由を確認
- 検討時と前提条件が変わっておらず、下げすぎと判断できれば買い
一方でドルコスト平均法と比べたデメリットも存在します。
- 手元に現金がある程度ある前提となる(銘柄数を絞って、投資額と手元現金を調整してください)
- 価格が上がり続けている銘柄では購入時期を逃す(欲しい銘柄の目星を複数考えてください。上がった銘柄は短期では縁がなかったと割り切って、割安になるタイミングを待つか別銘柄へ投資します。)
この辺がデメリットだと思います。
どの考え方にも良し悪しはあるかと思いますので、結局どのような方法が自分にとって一番ストレスをかけずに、合理的に考えて投資ができるかだと思います。
最後に、個人的には、信用取引は鋼の心臓をお持ちの方か、十分な余裕資金がある方以外はお勧めしません。投機ではなく投資をしているのですから。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
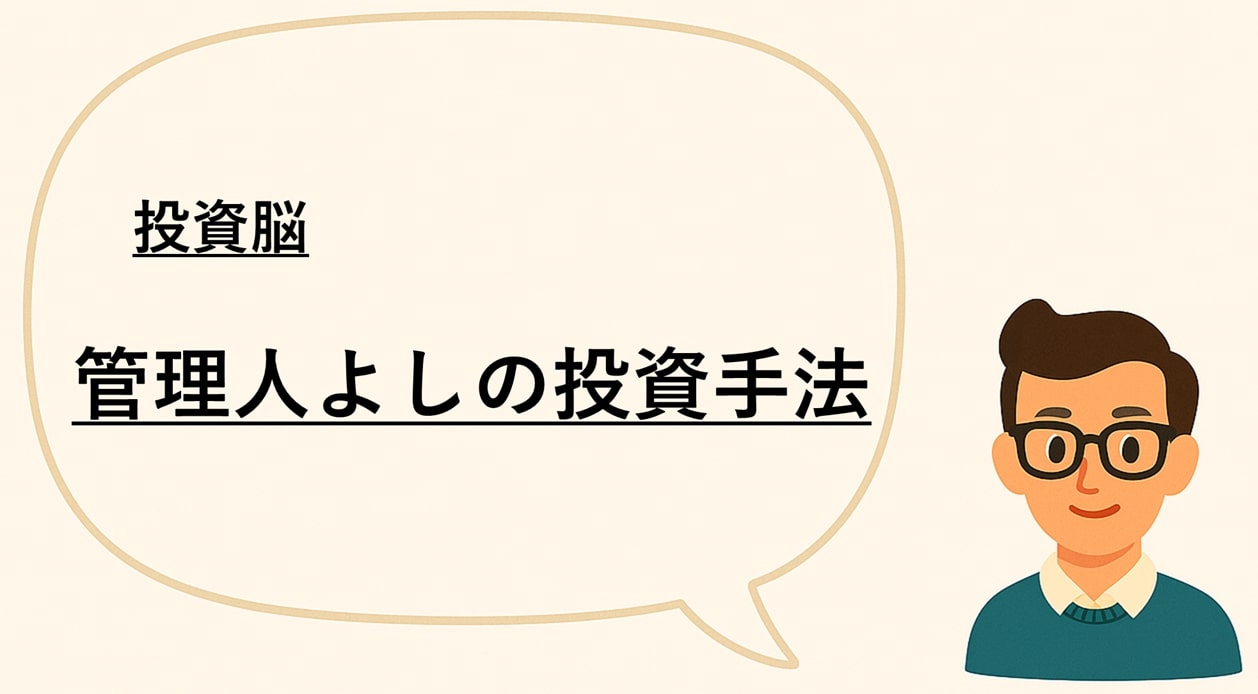
コメント