
こんにちは。よしです。
30代で純金融資産1億円を達成し、2025年12月現在1.5億円を超える純金融資産を保有しています。
現在体調を崩して働けていない状態の私は、それまでに配当収入を形成できていたことで日々のお金に関する心配が減りました。
その実体験をもとにお金に対する将来の不安があるけど、どういう基準、どういった考えで投資をすればよいのだろうという方向けに私の考えを共有いたします。
投資に対する考え方に関して記載していく本シリーズ(にする予定です)。今回は、インデックス投資に関してご紹介するとともに私が銘柄を選定する際の基準に関して紹介します。
前回の投資脳はこちら
結局インデックスが最強です。
まず、初めに。結局インデックス投資が一番楽です。
「投資ってよくわからない」
「勉強するのが面倒くさい」
という方は積み立て投資でインデックスの投資信託かETFを購入してください。インデックスとは市場の値動きを示す指数で、連動して価格が変動する商品を証券会社等が用意しています。
今回の投稿は最終的に「個別株に挑戦してみたい」や「個別株を買うならどういう基準で購入すればよいのだろう」という指標を探している方向けとなっています。深く考えたくない方や日々の値動きを気にしたくない方はインデックスを買っておけば間違いありません。
私自身積み立てでインデックス投資をしており、現在資産の2割程度を占めています。
なぜインデックスは強いのか?
以下がインデックスの強みです。
- 少額で始められる
- 値動きが確認しやすい
- 知識がなくても(個別株比)低リスクで始められる
- 投資先が分散している
- 様々な商品があり、好みのものを選べる
- 為替を考慮した商品もある
私が思う1番の強みは分散が効くことです。また、積み立ての場合はほったらかしでも資産形成ができる点も魅力的です。ただし、運用をプロにお願いしている関係で手数料がかかっていますので、手数料の割合には注意してください。インデックス投資は商品ごとにやっていることはさほど変わりませんので、できるだけ手数料が少ないものを選ぶのが王道です。
インデックスが最強なら、個別株なんて買う意味がないのでは?
「インデックスが最強なら、個別株なんて意味ないじゃん。」と思われる方もいると思います。もちろん、インデックス投資にもわずかながら問題があり、個別株投資にもうまみはあります。
インデックスのデメリット
- 手数料がかかる
- 好きなタイミングで買えない(積み立て投資の場合)
- 株主優待を得られない
- 投資したくない銘柄にも投資される
- 投資をしているという実感が得にくい
「好きなタイミングで買えない」という部分の補足をします。
株価は常に変動していますが、積み立て投資では購入のタイミングが指定できません。もちろん、どこが株価の底でどこが天井か判断することは通常難しいのですが、過去の株価推移や外的なイベントにより明確に市場や個別株が下落しており割安だと判断できることも多々あり、そういった”買い場”に自由に購入することができないことになります。
また、「投資したくない銘柄にも投資される」という部分に関しては、
例えば、ご自身が海運業界で働いているようであれば労働収入が海運由来のリスクを抱えていますので、海運業界の株式はポートフォリオから外した方がより安定度が増していることになります。また、中にはROEの低いゾンビ企業のような上場企業もありますのでそういった資金効率が悪い企業に強制的に投資されるようなリスクもあります。
また、「投資をしているという実感が得にくい」という部分に関しては、
インデックス投資はほったらかしできるという魅力がある一方で、特定業界のイベントに結果が左右されにくいことから社会の動きに鈍感になってしまうというリスクがあります。反対に個別株は、保有している業界に詳しくなります。
さて、私の投資基準をご紹介します
私は基本的に以下の基準でスクリーニングをかけて、銘柄を選定します。基準に合わなくても、将来有望だと思った銘柄や過去価格から割安だと思う銘柄を購入に選んでいます。
- PER×PBRが15倍以下(割安)
- 営業利益率が10%以上(本業で稼ぐ力有)
- ROIC10%以上(資本効率高)
- 自己資本比率50%以上(財務安定)
- フリーキャッシュフローが毎期プラス(安定)
- 配当利回り1%以上(配当を出している)
- 一人当たり営業利益の増加具合(本業で稼ぐ力有)
補足説明をします。読み飛ばしていただいてもかまいません。
一人当たり営業利益増に関して、
営業利益は従業員×一人当たり営業利益に分解して考えます。従業員の増加による収入増は今後収入が伸び悩んだ際に従業員のコストが嵩むので、一人当たり営業利益の伸びに注目して、稼ぐ力を判断します。
上記基準で抽出する際に気を付けて頂きたいのが、業界ごとの特徴です。例えば、有形固定資産を保有せず顧客にサービスを提供できるIT企業は利益率が高くでる傾向があります。固定資産の償却が軽いためです。一方でメーカーは有形固定資産が多く、償却が重いため利益率は低く出る傾向があります。また、安定している業界や競合が多い業界は利益率が低くなります。
上記基準では、業界ごとの数値特性が欠落していますのでそのあたりは慣れが必要が部分があります。
また、上記の財務数値基準以外に以下もしばしば購入の参考にします。
- 前日比3%以上値下がりした銘柄(一時的な理由で過度に安い可能性有)
- 利益が伸びているのに売られている銘柄(事業環境が変わっておらず、本業で稼いでいれば中長期で上がる可能性高。)
- 財務基盤が安定している銘柄(自己資本比率が高くともROE8%等)
- 平均給与が高い銘柄(優秀な人材集結)
- 成長している銘柄(成長枠)
- 優待利回りが高い銘柄(総合利回り)
- 自分が応援したい銘柄
上記の基準に合致するor合致しそうな銘柄を探しておき、時々株価や決算を確認。基準に入っていたら購入するという投資手法です。
まずはやってみること
つらつら書きましたが、まずはよさそうだなと思った銘柄を購入してみて、上がった理由。下がった理由。自分の仮定と何が違ったかというのを考えるのが重要かなと思っています。その際に、マクロによる影響がどの程度あるかによりますが、自分なりに考えるという部分が重要です。
まとめ
以上、私の投資基準を記載させていただきました。皆様の参考になりますと幸いです。
本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。
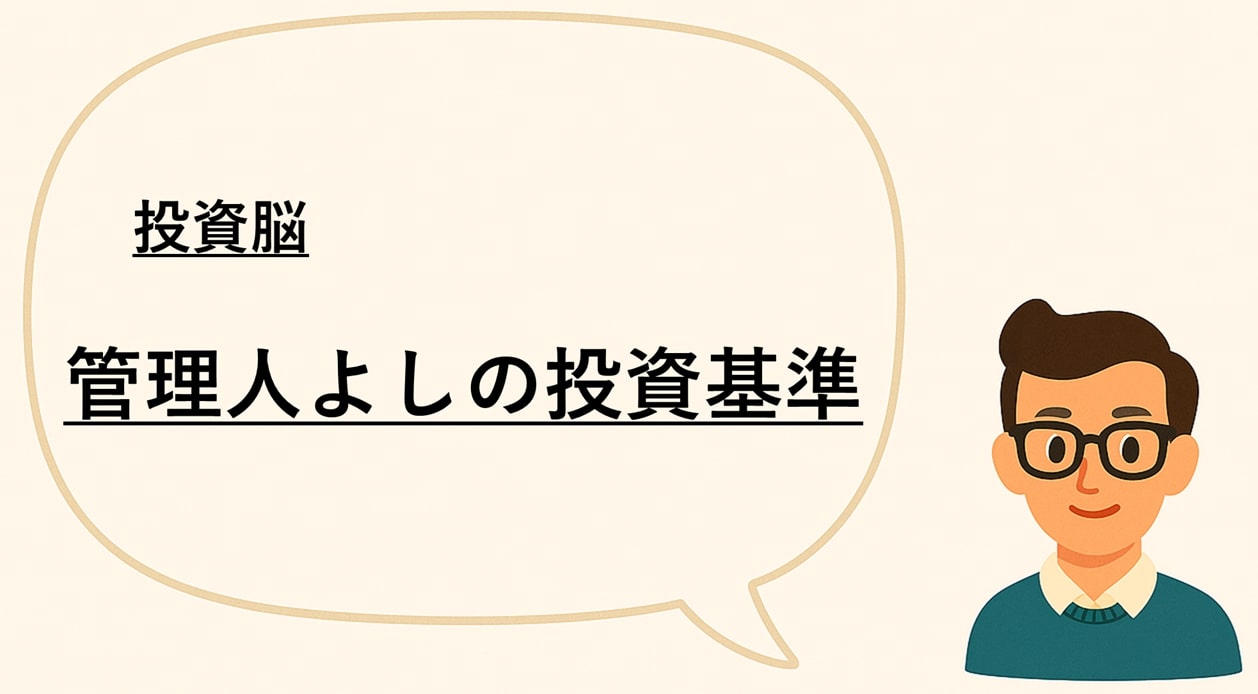
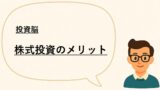
コメント