
こんにちは。よしです。
現在体調を崩して働けていない状態の私は趣味であるボードゲームでコミュニティを形成し、人との交流を図りストレスを減らすことができています。
ボードゲームは論理的思考力やコミュニケーション力の向上にも資すると思っています。
まだまだ趣味としてはマイナーなボードゲームを知っていただいので、有益な情報やもっとすきになってもらうための情報をまとめています。
こちらでは、タイトルの通りボードゲームの資産性に関して述べたいと思います。
ボードゲームは結構資産性があると思っています。
なぜかというと需給があっていないからです。その理由をご説明します。
そもそもインフレ下ではほとんどのものに資産性有
もちろんすべてが当てはまるわけではないのですが、昨今のインフレの世の中ではものの価格は上がるので、全く同じ需要が続くと仮定すると未開封を保った状態で長い間持っていれば大体のものは資産性を持ちます。
ただし、供給量の多い消費財は当てはまりません。
トイレットペーパーや枕の古いものがあってもお金を出して買いたいとはなかなか思わないですよね。
資産性があるという前提は代替品や需要が同様なのに供給が限られるようなケース、もしくは需要が減った結果わずかはあるのに採算性がとれないことから供給がされないケースです。
実はボードゲームは供給量が限られており、その分資産性はかなり高いと考えています。
購入したものの時間がなくそのまま未プレイで放置していたゲームは多々ある(ボードゲーマあるあるだと思っています。)のですが、時間が経過するとプレミアがつくことが多く買値より良い金額で引き取ってもらえます。
1万円のものが2万円近くで売れることもざらです。利益率でいうと、年率30-40%くらいの水準です。
プレイ済みのものでも購入時より大抵高く売れます。フリマサイトの普及で中古需要が増えたことも大きいですね。
ボードゲームで1万円!と思った(ボードゲーマ以外の)方、そうなんです。ボードゲームもルールが複雑で内容物が多いものは1万円を超えてきます。
10年もさかのぼると1万円超えのものは非常に稀だったのですが、最近はポンポン出てきます。
こういったコアゲーマー向けの商品が資産性が高い商品です。1,000円で買えるものは残念ながら資産性は低いと言えるでしょう。
結局は需給バランス
昨今のコメ価格高騰や、ポケモンカードの高騰に表されるように供給が限られ、それ以上の需要があれば必然価格は上がることになります。
ボードゲームはプレイ人口が少ないニッチな趣味ですから、特にコア向けの作品はなかなか部数が販売されません。
出版社は再販で売れ残るリスクを冒すよりは一定数が売れる新作にリソースを割きます。というわけで一度売り切れると再販はされず希少性が高くなるわけです。
そして、日本はボードゲーム後進国でして、海外で人気のあるものが日本語化されて市場に出てくるので、大体どの作品も面白く資産性の低いはずれというものが少ないというのが特徴です。
少し前は新規のコアゲーマは過去作は中古市場で探すしかありませんでした。
最近はビックカメラやヨドバシカメラをはじめとした家電量販店でも取り扱いが増え、テレビをはじめとしたメディアでも著名人がプレイしている姿を見るようになりましたので、一昔まえよりは再販されることが多くなってきたかなと思います。それでもまだまだ時期を逃すと手に入りません。
資産性がある作品
以下の特徴を持つ作品は資産性が高い傾向があります。
ぎりぎりの業界なので様々なおまけをつけることがあり、それが一般流通品との差を生むことが多々あります。
- 有名デザイナーの作品
- 10周年記念版のような豪華版
- クラウドファンディング限定のような限定版
- 長らくリメイク・再販がされていない商品
- 終売が宣言されている商品
- 日本語版
- 基本ゲームを要する拡張版(基本ゲームより数が少ないため)
- 小売価格が高い商品
最初の有名デザイナーの作品という点を除き、総じてそもそも部数が少ないという希少性が価格に反映されるということですね。さほど目利きはいらないというのがボードゲームの資産性の特徴です。
一方で、部数も限られていますので、やはりできればプレイする目的で購入していただきたいです。
私が手放している理由も棚のスペースがなく、泣く泣くという理由です。保管するスペースも限りのある資源ですので。
地政学というピース
ボードゲームの最大消費地はアメリカで50%以上を占めています。
人口に対するボードゲーマ人口という点ではドイツが多いです。2025年3月にはドイツの「ボードゲームを遊ぶ文化(Brettspiele spielen)」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。
余談ですが、日本はボードゲームといえば、将棋や囲碁、あっても人生ゲームという認識の方がまだ多く、カタンやカルカソンヌといったボードゲームはしばしユーロゲームという名で区別して語られます。
そして製造は中国です。現状中国でしか大量生産ができない生産体制だそうです。中国で作って主にアメリカへ。
ということで2025年上半期の米国関税騒ぎの際はボードゲーム業界は暗黒の時代を迎えると悲観的でした。
短期では両国の関係が悪化することはあれど目に見えて良化することはないかと思いますので、ますます小売価格は上がるのではと考えます。
中古でも昔のボードゲームがお手頃に思えてくる人が多くなるかもしれません。
再販に関しては、中国にしかない工場でフル稼働して製作している新作の合間を縫って行われるのでよほど人気があるものしか再販されないという背景がここにもあります。新作を販売したほうが売る側としてはリスクが少ないのです。
こちらの記事が非常にわかりやすいので、興味がある方はこちらも読んでみてください。※外部サイトにとびます。
https://note.com/behonest00033/n/n873237f3ad24
まとめ
プレイ済みでも購入時の価格で手放せるボードゲーム、趣味としていかがでしょうか。
ボードゲームプレイの最大のハードルはルール把握とプレイ人数の確保だと思っています。
是非プレイ人口を増やして後者のハードルを下げられればと思っていますので、興味がある方は試してみてください。
仮にプレイ人口が増えたことにより出荷部数が増え資産性は下がったとしても、プレイ人口が増えたことによりボードゲームが再販されやすい環境になる方が私としては嬉しいです。
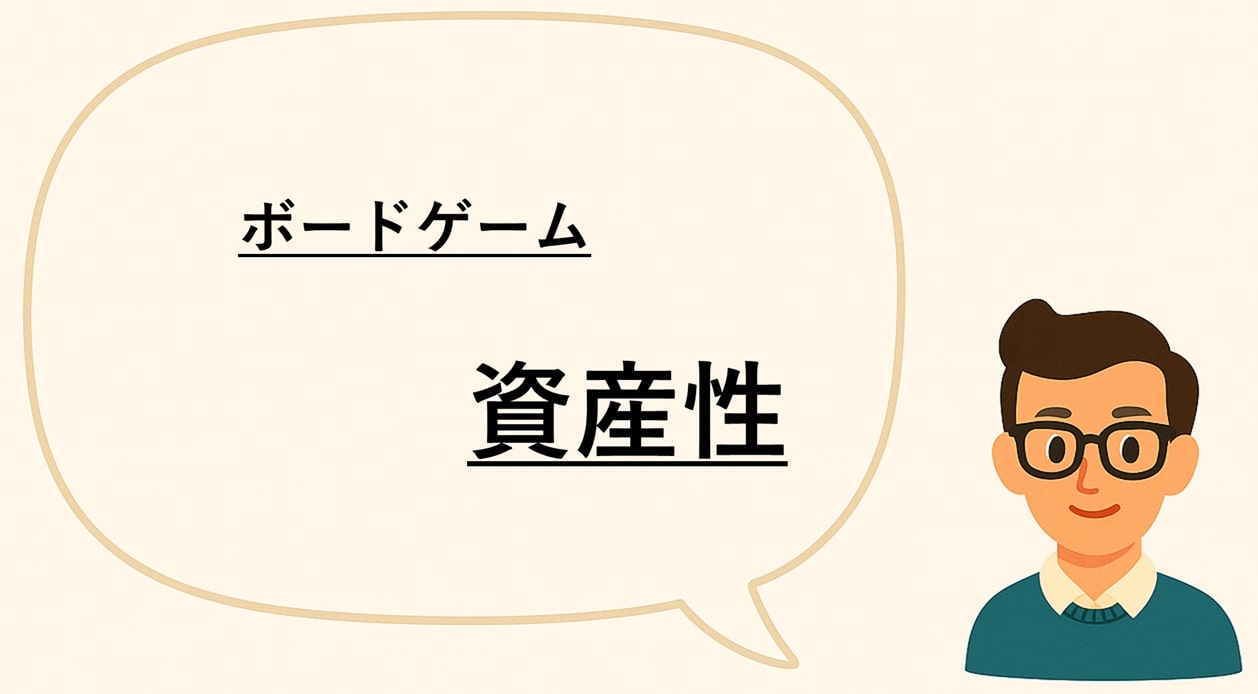
コメント